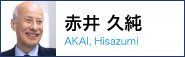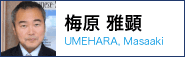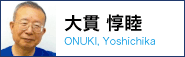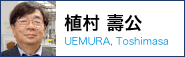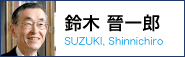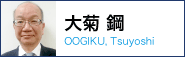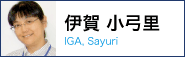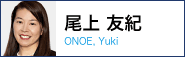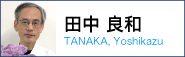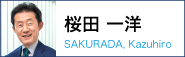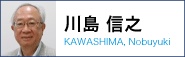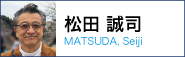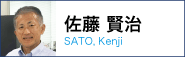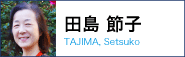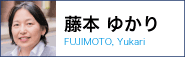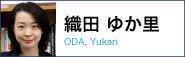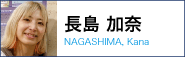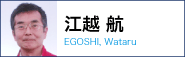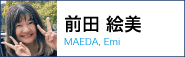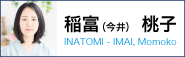先輩を訪ねて
Persons

現在はどのようなことをされていますでしょうか
ロート製薬の薬事部門に所属しています。薬事部門は、薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に基づいて製品の開発から販売後までをサポートする部門です。主な業務は「医薬品や医薬部外品の製造販売承認取得に向けた行政とのやり取り」「自社製品の広告が薬機法上適切であるかの確認」「薬事的観点からの製品開発サポート」です。
現在の活動(研究も含め)はどのようなきっかけで始められたのでしょうか
入社時は基礎研究開発の部門に配属され、日焼け止めの素材開発や各種測定技術の開発に携わっていました。
2024年の人事異動で現在の部署となりました。薬機法の「や」の字も知らない状態からのスタートでしたが、日々勉強を続けながら業務に取り組んでいます。
大阪大学理学研究科・理学部時代に、心がけていたこと・大切にしていたことは何ですか
研究にきちんと取り組むことは前提として…。
もう一つ大切にしていたことは「研究室以外にも自分の居場所を作ること」でした。居場所が一つしかないと、そこで躓いたら一気に”独りぼっち”になってしまいます。私の場合、「超域イノベーション博士課程プログラム」というリーディング大学院を副専攻で履修しており、他研究科の学生と関わる機会が比較的多くありました(卒業後の今でも、なんやかんやで機会があれば集まる仲です)。また研究科内でも、他専攻の学友とゲーム会を企画するなど、とにかくコミュニティが一つにならないように心掛けていました。もちろん個人差はあると思いますが、本業の研究でしっかり頑張れるように、このメンタル維持法は私には有用だったと今でも思います。
「大阪大学 超域イノベーション博士課程プログラム」修了生インタビューページはこちら
大阪大学理学研究科・理学部時代に印象的なエピソードがあればお教えください
特に印象に残っているのは2つです。
①新しい知見や技術を得るために、他大学に訪問させてもらう機会をいただいたことです。例えば、ハエの交尾の観察方法を学びに東北大学を訪問したり、蚊の飼育方法や遺伝子組み換え技術を学びに東京慈恵会医科大学にて修行させていただいたり…。様々な機会に恵まれていたと思います。
②博士論文発表時、各新聞社の皆様を相手に記者会見をし、後日某全国紙の科学欄で取り上げていただいたことです。基礎研究が一般の皆様の目に留まることは正直なところ少ないのですが、「研究をやっていてよかったな」としみじみ思った瞬間でした。
稲富(今井)氏の博士論文に関連する記事はこちら
これからの大阪大学理学研究科・理学部について、提言等ありましたらお教えください
私が卒業してからのイメージにはなってしまうのですが、博士後期課程学生の企業就職への心理的ハードルが低くなったように見えます。これは「学生の将来の選択肢が実質増えた」ということで、とても良い変化だと思います。
学生のうちから変わらずに一つのことに全てを注ぎ込む人生も素晴らしく、心から尊敬しています。しかし、学校を卒業してからも長く続く人生、途中で別の道に進みたくなっても不思議ではありません。大阪大学には、研究に進む方・違う道に進む方の両方を輩出し続けていただきたいです。
今後やってみたいことはどのようなことでしょうか
様々な一般用医薬品(いわゆる薬局で市販されている医薬品)の製造販売承認取得にチャレンジしたいです。医薬品は、モノによって承認取得までのハードルが異なります。そのハードルは、医薬品を適切に、効果的に、そして安全に消費者の皆様にご使用いただくために必要なものですが、それを乗り越えた先で、また新たなお客様のニーズに答えることができると思っています。
また、新しいことを知るのが単純に好きなので、医薬品について様々なことを勉強できるのも楽しみです。
理学友倶楽部の部員にメッセージをいただけますでしょうか
「自分の持つ【純粋な興味】に全身でぶつかっていけるのは学生の特権だ」と、卒業してから本当に強く思います。全力で取り組んだ経験は、たとえその結果がわかりやすい形にならなくても、間違いなく人生の糧になると思います。学生の皆様、ぜひ思いっきり研究生活を楽しんでください!
最後にひとこと
今回、このような寄稿の機会をいただいて大変うれしく思います。博士後期課程卒業→アカデミア…といったような“王道ルート”を歩んでいるわけではないのですが、「こんな卒業後のキャリアもあるんだな」と、一例としてご覧いただければ幸いです。